回転アニメーションの歴史
絵や図形が描かれた円盤をまわしてみると、図柄が動いて見える仕組みは、1832年にベルギーの物理学者ジョセフ・プラトー Joseph Plateau (1801-1883)が発明しました。「フェナキスティスコープ」という名前です(*1)。これは映画の映写機やアニメーションの始まりとされています。日本では、後の時代になってアニメーション作家の古川タクさんがこの装置を「おどろき盤」と名付けました。
円盤の上の絵や図形は、少しずつ変化していくように描かれているのが特徴です。回る円盤を直接見ても、動きを見ることはできませんが、小さな穴(スリット)を通して円盤をみると…? 「残像効果(*2)」という視覚の働きと、こうした装置が組み合わさることで、動かないはずの絵が動いて見えるアニメーション表現が生まれました。
19世紀のヨーロッパでは、この「フェナキスティスコープ」をはじめ、様々な回転アニメーション装置が流行し、おもちゃとして親しまれていました。色んな絵柄と装置がセットになっており、いくつもの絵柄を楽しめるようになっていました。
回転運動によって絵を動かして見る19世紀の原始的なアニメーション装置には、様々なタイプのものがあり、そのうちのひとつ「ゾートロープ」は今日でもとくに有名です。
- *1「フェナキスティスコープ」
- ギリシア語で「だます」という意味の言葉と、視覚装置を意味する「スコープ」という言葉が組み合わされた造語です。
- *2「残像効果」
- さっきまで見ていた光や映像が、その光が消えた後でも残って見える現象や、視覚の働きのことを言います。
東京都写真美術館のコレクションより

おどろき盤(フェナキスティスコープ)
一枚の円盤にえがかれた絵柄を鏡に映して楽しむタイプの回転アニメーション。
東京都写真美術館 蔵 19世紀

ヘリオシネグラフ
スリットが入った黒い円盤と絵柄がある円盤が二枚組になっていて、鏡に映さなくてもアニメーションを見ることができる。
東京都写真美術館 蔵 19世紀

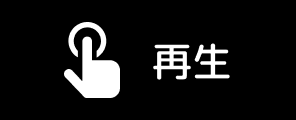


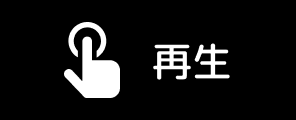


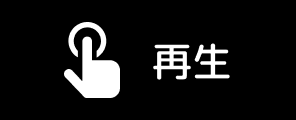


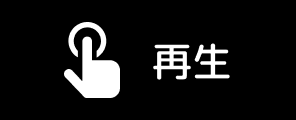

19世紀回転アニメーションの絵柄
19世紀の回転アニメーションには、人や動物の面白い動きから、図形を組み合わせた動きなど、アニメーションの面白さを効果的に見せるアイデアがいっぱい!一枚の円盤の中の、中心部分とその外側部分が別々の層になっていて、それぞれがちがう絵柄になっているものが多い。当時の人々は、さまざまな絵柄の円盤をフェナキスティスコープやヘリオシネグラといった装置に取り付けて、アニメーションを楽しんでいた。
東京都写真美術館 蔵 19世紀

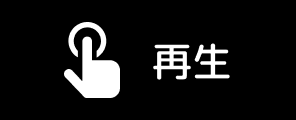

ソーマトロープ
フェナキスティスコープよりも古い発明。一枚のカードのオモテとウラを速いスピードで交互にみると、二つの絵が重なったり動いて見える。
東京都写真美術館 蔵 19世紀

ゾートロープ
回転する筒の内側にある絵柄を筒に開けられたスリットからのぞくことでアニメーションを見ることができる。この方式では、一人ではなく何人かで楽しむことができる。
東京都写真美術館 蔵 19世紀